~施設職員のお仕事~
1999年3月、知的障害児施設職員に向けて、綴ったメッセージを加筆・再編集し、振り返ってお届けします。25年以前のことなので制度や施設のスタイルが現在(2024年)と違っていますが、「施設職員の仕事」の基本的な考えには変化がありません。

1 生活の幅を拡げる
「生活の幅を拡げる」という言葉を使いますが、1999年当時鳥取大学教育学部の田丸敏高さん(福山市立大学学長の後、現在は鳥取大学名誉教授)から、「知的障害があって能力の発展や成長は難しくても、その幅は無限に拡がる」という言葉を聞いたときに「ああ、そうか」と思い、それから私もいろんな場面でこの表現を借りています。文字が読めるようになったら、いろんな本を読むことができるということですね。心理学の本も物理学の本も、哲学の本も沢山の小説も読むことができます。そのことでいろいろな知識や経験を得ることが可能となります。ひとつの能力で行為の幅を広げることができます。
案外、私たち大人は、了見が狭くて幅を拡げると言うこと自体を狭く考えてしまっているという感じはします。文字を読めれば、もっといろいろな情報を得ることができる、といった便利さに価値をおいてしまいす。もっと、柔らかく考えてみてはどうでしようか。
役に立つことばかりではなく、実際の生活に直接、役にたちそうでないこと。例えば文字を読めること(スキル)に比べると音楽を聴く・楽しむというは直接生活の役には立ちません。それでも、音楽を聴くことには、文字を読むことと同じくらい限りのない無限の幅があります。それは音楽にいろいろなスタイルがあるからです。演歌やポップス、ダンスやジャズという表現を受け止めることができればそれだけで、幅が拡がったと考えることができます。勿論、好きな音楽とそうでもない音楽があります。演歌が好きといっても、あの人のこの歌が好き、この人の歌はそうでもない、というような好みの問題があります。音楽を聴くときに誰でも好みがありますから、音楽の選び方はほとんどその人に任せてしまうのがいいと思います。知的障害児の施設での生活は音楽に限らず、何となく「その人にふさわしい」設定をしてしまいます。そのうちのほとんどが正しい設定のなのですが、やはり、必ず正しいということではありません。本人の意思を確かめなかったり、その子どもの好みとの調整をしないまま、職員が勝手にふざわしい設定をしてしまってはいませんか。大人が音楽の好みを押しつけられるのは、とても迷惑なことだと感じるでしょう。子どもも同じで「私自身」の主体性が必要になります。そして、何か押し付けられたときに、子どもが「NO」といった時、それを「わがまま」と表現したりします。
「幅を拡げる」のは「とても」あるいは「まあまあ」難しいことなのです。そして、一人で取り組むには、時間がかかること、そして大小の危険が伴うことなのです。そこに施設職員の役割があるのだと思います。そしてそれは施設職員を含む、様々な周囲の人々との関係の中で育ってゆくのです。

2 子どもたちは危険が好き
子どもの生活や経験の幅を拡げるというときに子ども達や私たちの重要な法則を知っておかなければなりません。小さな子どもと道路を歩いている時に気が付くと思います。障害があるということに関係なく子ども達は道路の端っこや歩道の縁石、溝があれば溝の縁を歩くものなのです。子ども達の行動はいつも危険に満ちています。わざわざのように危ないところを歩いたり、走ったりするものなのです。そして実際に溝に落ちたり、転んだりするのです。大人は、もっと安全なところを歩くようにと子ども達に話しますが、子ども達はそういう危険が大好きで、私たち大人が思うように振る舞ってはくれません。子ども達というのはそういう危険なところを歩むものだと理解した方がいいのです。子どもで経験が乏しいから。危険なこと(愚かなこと)をするのではありません。そうやって子どもは安全と危険の狭間を歩いて成長するのです。危険が完全に取り除かれ、すべてが安全という生活で成長した子どもを考えてみてください。その子どもはその生活から外に出ることが一生できないまま成長します。施設では、「施設ホスピタリズム」と表現したり、単純に「過保護・過干渉」と表現したりすることもできます。つまり、子ども達は自分のできるギリギリのところまでを経験の幅として持っています。たとえそれが危険なことであってもです。

3 ジャングルジムに登る
ジャングルジムを例にして考えてみましょう。ジャングルジムの2段目から3段目によじ登る能力を身につけると10段目から11段目によじ登ることは同じですからできて当たり前です。実際には、地上からの高さが違いますから、子どもにとっても大人にとっても感ずる(予想する)危険度は違ってきます。一度に一段ずつしか登れないのが一度に3段ずつ登れるようになれば能力の向上です。一段ずつでも3段ずつでも登れることには変わりないのでジャングルジムでは、どちらの方法でも一番てっべんまで登ることはできます。
子ども達は危険を感じながら、頂上をめざして登ります。登る動機は余り関係ありません。他の子どもが登っているからかもしれません。大人が上か下のどちらからか、励ますからかもしれません。もしかしたら、頂上まであがって遠いところを眺めたいのかも知れません。こんなときこそ子ども達は力を発揮します。ジャングルジムをよじ登るという単純な能力を充分に発揮して経験の幅を拡げて行きます。大人は頂上まで登ることができる子どもを肯定しますが、同じくらいそんな危険なことをする子どもを否定してしまいます。それは私たち大人は、あらかじめ危険を知っていて予想できるからです。子ども達は危険を知りません。何故、知らないのかというと知る必要がなかったからなのです。それに知っていればそんなことをしないのが普通です。子どもはそんなことを知らずに育ちます。ジャングルジムのてっぺんに登って、もしもおっこちたり、バランスを崩して落ちそうになって初めて、ことの重大さと危険を知るのです。それからは、より安全に登る慎重さを手に入れて、ジャングルジムのてっぺんを征服するのです。子ども達はいつもギリギリのところまで幅を拡げて、ギリギリの線の上で生活しています。一方、大人達は自分や子どものギリギリの線を知っていますから、ギリギリの線よりもっと安全な場所にいることができるのです。大人が生活の幅を拡げるというのと子ども達が生活の幅を拡げるというのはまったく違っているということを知って欲しいのです。大人がギリギリを知っていて(常識として)子どもが知らないということなのです。そんなときに大人の役割が見えてぐると思います。そしてこんなこともその子どもと大人の関係の問題なのです。

4 大人は身勝手
生活や経験の幅を拡げるということは、子どもが主体的に危険を乗り越えてゆくことなのです。ところがほとんどの大人は「経験の幅を拡げるのだ」といってはいろいろなチャンスを与えて、ジャングルジムのてっぺんまで登れるようになると「良かった、良かった、できたねぇ」と誉めるのです。ここまで、誉めるところまではいいのですが次に続くのは、「勝手にてっぺんまで登っちゃいけないよ」とか「今度はもっと下で遊びなさい。」と余分なことをいってしまうものです。子どもは自分の持っている幅のギリギリのところまで行きますから、当たり前のようにいつもジャングルジムのてっぺんまで登るのですが、どうも、私たちの設定している「生活の幅を拡げる」とか「経験の幅を拡げる」というのは、チャレンジして獲得した喜びを発揮するチャンスを無駄にしているような、そんな気がしてなりません。
子どもにとっては、一旦、広がったらそれが普通のことであって、特別なことではないのです。私たちの施設での買物も同じだと思います(1999年頃、皆成学園では、「街に出よう」、「生活を取り戻す」というテーマでのチャレンジをしていました)。最初は特別なこととして、計画し支援し実行します。でも、そんなふうにして(たとえ大人に手伝ってもらったとしても)初めての買物が出来たという経験は次の回からは普通のことになってしまうのです。それを証拠に何度かの経験で子ども達は買物に出向くときに自分が何を買わなければならないのかを知っていたり知ろうとしたりしています。当たり前のことが当たり前でなければ特別なことなのですが、たとえ大人にとって特別なことでも既に子ども達は普通のこととして生活の一部に取り込んでしまっているということなのです。
子どもの施設の多くにその施設特有の文化があると思います。今は減ってきているのでしょうが施設職員を「先生」と呼ぶ習慣があります。これは一種の構造化です。「先生」と呼ばせることで子どもと職員の関係を規定しようとしているのです。また、便利な方法でもあり、「先生」って呼んでおけば、誰か分からなくてもこっちを向いてくれます。つまりは、名前を覚えなくて良い(個体識別がいらない)のです。子どもの家族にとっても同じです。ほとんどは「〇〇先生」と苗字や名前の後に先生とつけますが、うっかり忘れた時には「先生」って呼んでおけばいいのです。施設の外に出て、誰かを先生と呼ばない柔軟性のある方はいいのですが、そうでない方は、戸惑うでしょう。これも施設ホスピタリズムのひとつだと思います。施設で「先生と呼び合ったり、子どもに先生と呼ばせるのは止めよう」とキャンペーンをしたことがあります。経過の中である職員が子どもに「〇〇さん」と苗字で呼ばれた時に「〇〇先生と呼びなさい」と叱りつけた職員がいましたが、柔軟性のないのは職員の方です。

5 施設ホスピタリズムのこと
子どもの環境から危険や失敗を取り除きすぎると子どもの成長を阻害します。また、生活でのさまざまな課題を施設内で完結しようとするとそれも、子どもには良くないことだと思います。よく「地域(社会)に開かれた施設」という表現がありますが、「地域の人が利用する」という限定的なことでは開かれているのでしょうが、施設での生活が子どもにとって開かれているという施設は少ないようです。施設内に閉じ込められているとは言わなくても、世間の標準が施設に取り入れられているかというかなりの疑問が湧いてきます。
施設での生活は、やはり特殊な環境で「養護」、「保護」の名目でできるだけ危険や失敗から遠ざけようとします。それは決して良くないことではありませんが、すごく良いことでもないのです。子どもの成長・発達の過程で「自分を高めようとする子どもの心」の方が「危険を冒さないこと」よりも大切なことなのです。「子どもには危険が必要」といっても、そこに大人の役割があります。子どもに一番近い職員(保育者)は、「子どもに失敗をさせない」ことが素敵な支援だと勘違いしているのです。子どもが失敗したら職員自身の責任にように思ってしまうのです。大人の役割としては「失敗しても大丈夫」という支えが大切です。一方で、取り返しのつかない失敗もあるのですが、それは職員の責任ではなく、施設管理者の責任です。職員に対して適切なスーパーバイズや実用的な研修をしていなかったということなのです。
前述の田丸敏髙さんの著書「子どもの発達と社会認識」のテーマと内容を踏まえれば、チャレンジを奪われることは、充分に「施設ホスピタリズム」となりえるのです。
25年前、皆成学園指導部長の時に職人に宛てた文章が片づけの時に出てきました。13項目に亘って思い付きを書き綴って、25ページの冊子にして職員に届けました。今になって、読み返すとなかなか面白いことを書いているなぁと自分なりに感動しています。今回は部分で「9 幅を広げる」の項を再編集、再構成しました。残り12項目あります。順次、お届けしたいですね。最後まで読んでいただいてありがとうございました。
当時 1999年3月1日 鳥取県立皆成学園 指導部長 西井啓二
現在 2024年3月23日 和泉屋与兵衛 代 表 西井啓二

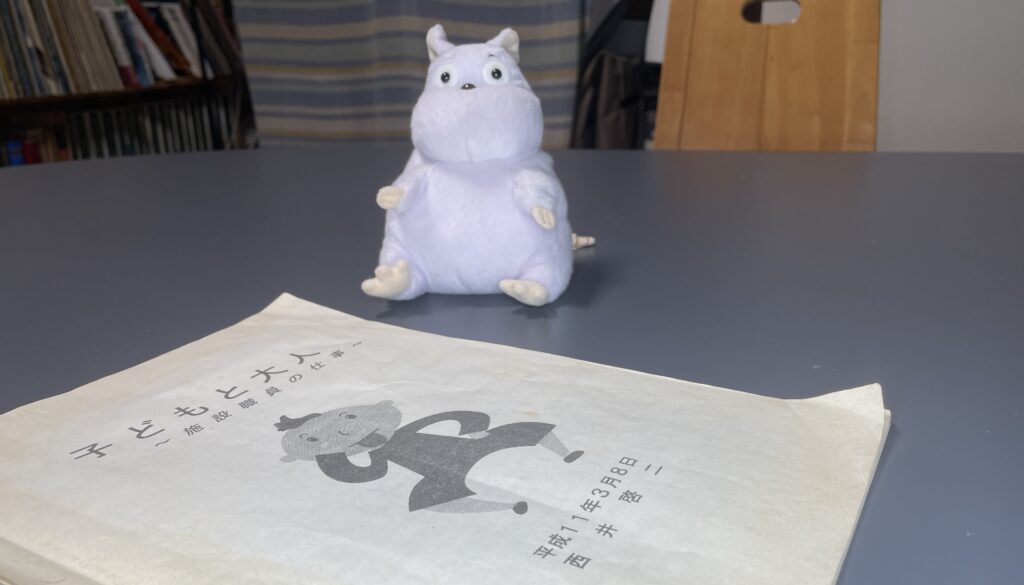
コメントを残す